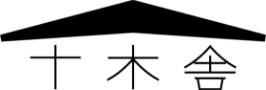有栖川の家 上棟しました!
京都を囲む山々では新緑の美しい季節になってきましたね。
さわやかな春の風をきってのドライブや山や海でのバーベキューなど
GWの行楽を楽しんでおられる方も多いかと思います。
さて今回の現場日記は先日上棟を終えました、「有栖川の家」からの
お届けです。
今までのお住まいを解体して、今回新たに建て替えをなさいました。
閑静な住宅街とあって、建て方当日は朝から大工さんの掛け声と
材木を組む音が響きます!
梁を組む大工さんと下で柱を支える大工さんの息もぴったり。
このようにお隣様との距離が少し近い現場では特に慎重に工事を
進めなければなりません。
クレーン車が到着。これで大きな梁も釣り上げることができ、作業もはかどります。
見る見るうちに2Fの床の梁が組まれていきます。
さすが大工さん、梁の上だって平気な顔で歩いて行きます。
2Fの床組みが終わると屋根を組んでいきます。だんだんと高くなっていきます。
屋根の上ではもくもくと作業を進める大工さん。
この日は天候にも恵まれ、予定していた上棟の作業を終えました。
事故もけがもなく屋根仕舞まで終えるとホッと一安心です。
こちらの紙の養生が貼られている梁はリビングの天井に現れてくる梁です。さてどんな仕上がりになるのか今からとても楽しみな予感が・・・
こちらの「有栖川の家」今後の現場日記もお楽しみに!
森谷