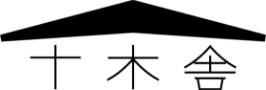秋も深まり、現場への移動中に車窓からは綺麗な紅葉が目に留まります。
今年の秋は度重なる台風の影響で、建築現場も少なからず影響を受け、
台風被害の復旧作業と資材不足が重なり、各業者・職人さんもフル回転の日々を過ごしております。
今回の現場日記は先月の台風25号の接近で、見学会が中止となりました
「有栖川の家」。実例紹介に先立って、その一部を現場からお届けします。
まずは十木舎がこだわる階段の造作から。
十木舎の階段は「総ヒノキ造り」が特徴です。

大工さんが一枚一枚丁寧に手加工を施し、施工されていきます。

階段の施工は大工仕事の中でも、特に技術の必要な個所の一つで、
プランにしたがって正確に造っていく技には、毎回感激します。

まさに吟味された材料と大工さんの技術との融合です。


だんだんと出来上がっていく様は中々みられませんので、今回ご紹介いたします。

総ヒノキ造りのひな壇階段の完成です!
合わせて2F階段の手すりも無垢材で造作。

杉の赤柾板を使い端正で落ち着いた雰囲気。
手触りも杉特有の柔らかみがあります。
続いてはダイニングテーブルのセットです。
栗のフローリングには風合いが似たタモが良く合うと、
お施主様自ら弊社の一枚板の倉庫へお越しいただき、タモの一枚板を吟味されました。

ダイニングテーブル用のタモの一枚板加工中。
合わせてベンチには木目が美しいタモの良材。

背もたれ用のタモ材は木目の良いところを見極めます!

ベンチと程よい角度をつけた背もたれの造作

作りつけのダイニングテーブルとベンチはお施主様のご要望に合わせてあつらえたオリジナル。

すべてタモで仕上げました。
このほかにも障子を随所に採用され、落ち着いた雰囲気のお宅が完成しました。
(ダイニングの月見障子)

「有栖川の家」この続きはまた実例紹介をお楽しみに!
いよいよ今年も師走の声が聞こえてまいりました。
何かと気ぜわしくなりますが、皆様もお体には十分お気をつけください。
森谷